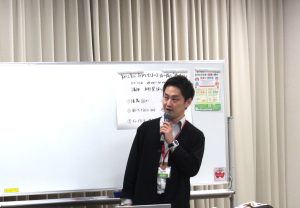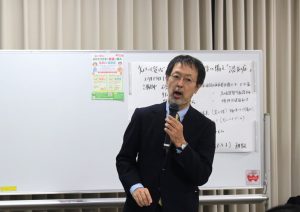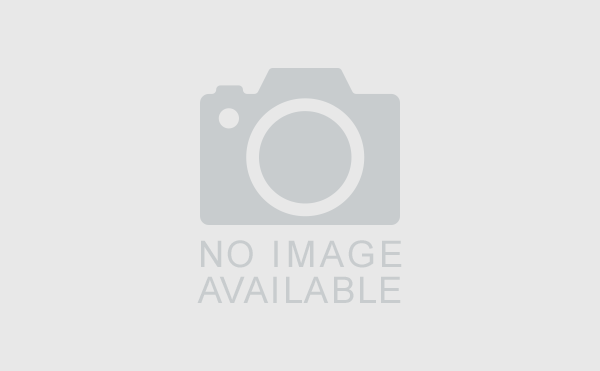令和6年度 知って安心 おひとりさまの老後の備え「住まい」/「認知症」
開催日・開催時間
第1回 令和6年12月6日(金)19時00分~21時00分第2回 令和6年12月13日(金)19時00分~21時00分
対象
テーマに関心のある人(50~60代くらい)事業報告
2050年には単独世帯(おひとりさま)が全世帯の44%になり、その半数近くが高齢者という推計(厚労省)があります。家族の姿が急速に変化する中、おひとりさまが社会的制度やサービスを使えなかったり、地域とのつながりが少ないなどの理由によって困難を抱えることがあります。そこでおひとりさまが老後に心配を抱きやすい「住まい」「認知症」を取り上げ、それに備える知識や情報を伝える講座を開催しました。
第1回は、居住支援を行う社会福祉法人天竜厚生会の水野晃佑さんをお迎えし、居住支援の現場から見えるおひとりさまの「住まい」に対する困りごとや支援の実際についてお話ししていただきました。
はじめに「住まい」とはどういうものか。「家」があれば良いのではなく、「住まい」は就労や社会とのつながり、あらゆる生活面に関係していること。「住まい」探しで困難を生じる原因は、個人の経済的な困窮だけではなく、労働環境や家族の形態の変化、既存の制度で対応困難などにもあることを説明されました。
ここで参加者が「住まい探しで困りそうなこと」「生活するのに困りそうなこと」を個々にシートに書き出し、グループで共有しました。支援の現場において実際に困ることの事例として水野さんが紹介された中には、不動産業者とのやり取り、引っ越しの大変さ、病院やスーパーが近くにないなどの他に「頼れる人がいない」というものもありました。
居住支援の現場において入居が決まらないケースもあり、その具体的な事例は大変参考になりました。まとめとして、「住まいをはじめ生活の困難は誰にでも起こり得る。何かが起きてから誰かとつながるのではなく、普段からの『つながり』が大切です。」とお話しされました。
第2回は、「認知症」をテーマに、医師、看護師、相談員の立場から3名の講師の方々にお話しをうかがいました。
医師の立場からは、浜松市認知症疾患医療センターセンター長 磯貝聡さんに認知症の年齢別の有病率や、軽度認知障害について、認知症と物忘れの違い、記憶の障害だけではない認知機能障害についてなどを説明していただきました。認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、令和5年に認知症基本法が制定されました。認知症の人が尊厳や希望をもって暮らすためには、人とつながり、老後の医療や介護の方針を予め話し合い、自分の生き方、考え方を伝えておくことが大事と話されました。
ここで講師は同センターの老人看護専門看護師 佐藤晶子さんにバトンタッチ、浜松市発行の「人生会議手帳」を用いて、「もしものとき」どのような医療・ケアを受けたいかを記録することについて教えていただきました。「自分の人生の最終段階について考えるのはとても大変なこと。この手帳は、気分の落ち着いている時に、書きたいことだけを書くもので、何度書き直してもいいし、自分の大切にしていることを、大切にしている人に話すきっかけにもなります。今すぐにでなくてもいいので一度読んでみてください。」と話されました。
次に、同センター精神保健福祉士 岩口雅代さんが相談員の立場から、「自身の老いをどう備える?~安心した老後を過ごすために~」として、任意後見制度、財産管理等委任契約、死後事務委任契約といったすこし難しい制度や手続きについて、講師3人で寸劇風にわかりやすく説明してくださいました。お話しの最後に相談先や支援先の紹介がありました。岩口さんは講義の中で、「老後を生きるには、人の助けが必要になるという覚悟を持っていて欲しい」と話されました。助けてもらう力の必要性を感じる印象的な言葉でした。
最後に、余命わずかの想定で自らの価値観を考え話し合う「もしバナゲーム」を佐藤さんに教えていただきながら、グループごとに行いました。自分が大切にしていることがどんなことかあらためて知るきっかけになったのではないでしょうか。
参加者からは 「必要なことと思っていながら、後回しにしていた内容でした。」「今日のお話で次のステップへ進めるきっかけになりました。」「なかなか聞けないことばかりでした。」「これからの生活、考え方に有意義でした。」「つながりが大切だということを知りました。」などとても前向きな感想をいただくことができました。
今後もあいホールでは、おひとりさまが自ら行動して備え、安心して老後を過ごすための講座を開催していきたいと思います。